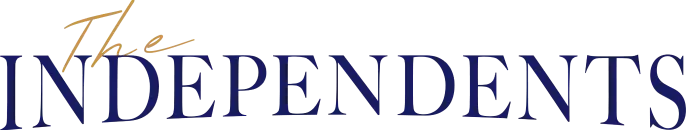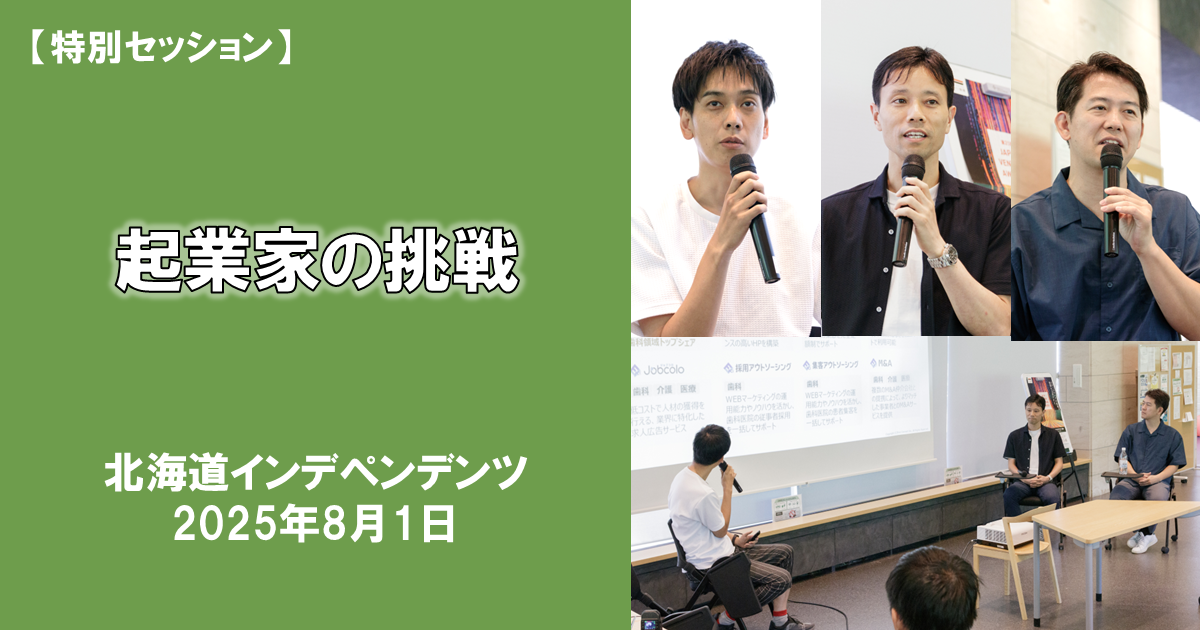<イベントレポート>
2025年8月1日 北海道インデペンデンツ
@ 北海道大学エンレイソウ
+ Zoom ウェビナー配信
■ イベント詳細 https://www.independents.jp/event/769
<特別セッション>北海道インデペンデンツクラブにて開催された特別セッション「起業家の挑戦」では、株式会社ファーストコネクト代表取締役の宮副俊彦氏をモデレーターに迎え、株式会社フーディソン(東証グロース) 代表取締役CEOの山本徹氏、株式会社ヴィリング代表取締役の中村一彰氏がパネリストとして登壇されました。 この3名は、株式会社ゴールドクレスト(東証スタンダード)に新卒同期として入社後、転職先の株式会社エス・エム・エス(東証プライム)でも再び同僚となり、その後それぞれ起業された経営者仲間です。本セッションでは、バイアウトに至る意思決定の舞台裏や、上場後の経営課題、M&A戦略に至るまで、リアルな視点で語られました。 |
||||
| (モデレーター) 株式会社ファーストコネクト代表取締役 宮副 俊彦 氏 |
(パネリスト) 株式会社フーディソン 代表取締役CEO 山本 徹 氏 |
株式会社ヴィリング 代表取締役 中村 一彰 氏 |
||
 |
 |
 |
||
■ IPOか、バイアウトか — 起業家が迫られる究極の選択
宮副:本日は、起業家のEXIT戦略として大きなテーマであるIPOとバイアウトについて、それぞれの経験者に深く切り込んでいきたいと思います。まず中村さんは、元々IPOを目指していたと思いますが、最終的にマネックスグループへのバイアウトという道を選ばれました。この意思決定の背景には何があったのでしょうか。
中村:創業当初は、社会的なインパクトを創出するために事業をスケールさせる手段として、IPOを夢見ていました。しかし、コロナ禍で教室事業が大きな影響を受け、資金繰りが厳しくなったのが大きな転機です。なんとか危機を乗り越え、1.5億円の資金調達を目指して動いていたのですが、労働集約的な事業モデルということもあり、調達は難航していました。そんな折、マネックスグループから、「3年間で毎年1億円、合計3億円を増資して事業を伸ばさないか」という提案をいただきました。それまでM&Aは頭の片隅にはありましたが、本気で考えてはいませんでした。しかし、自分たちで調達を目指す金額の倍であり、何よりコロナのような不測の事態が起きても雇用を守れるという安心感は非常に大きかったです。
宮副:マネックスからの提案ありきで、他の選択肢を比較検討することはなかったのですか?
中村:ありませんでした。マネックスとの話がもし不調に終わっていれば、再びIPOを目指していたと思います。金額交渉もほとんどなく、ロックアップという言葉も一度も出ませんでした。契約書上は5年間の事業計画提出が求められていましたが、ペナルティなどはなく、信頼関係に基づいたディールだったと感じています。また、既存株主への説明においては、以前、投資家からの助言で第三者機関に依頼して算定していた株価評価額があったため、それをベースに交渉を進めることができ、非常にスムーズでした。
宮副:もし仮に、最初からバイアウトを狙って起業するとしたら、事業の進め方は変わっていましたか?
中村:全く違う発想になったと思います。まず、大手企業が参入してこないようなニッチな領域を選びます。そして、スケールや利益を追求するよりも、とにかく優れたコンテンツやプロダクトを作り込むことにリソースを集中させたでしょう。事実、マネックスグループが私たちに関心を持ってくださったのも、「STEAM教育領域で、最も良いコンテンツを豊富に持っているのはどこか」という視点で探した結果、弊社だったと聞いています。プロダクトの価値を磨き上げることが、結果として最良の選択肢に繋がるのだと思います。
 写真左から)中村氏、山本氏
写真左から)中村氏、山本氏■ IPO後の変化とM&A戦略
宮副:次に、IPOを達成された山本さんにお伺いします。上場を経験してどのような変化がありましたか?
山本:最も大きな変化は、株主構成が変わり、特に機関投資家との関係性が生まれたことです。上場前もVCなどから出資は受けていましたが、事業をしっかり伸ばすことが最大の責任でした。元々、長期的な視点で「生鮮流通に新しい循環を作り出す」という挑戦をしていたのですが、上場後は日々の株価という形で常に評価に晒され、より短期的な成果を求めるプレッシャーが格段に高まりました。そのプレッシャーに流されて短期的な経営に陥らないよう、強い意志を持って長期的な視点を維持し続けるバランス感覚が、この1、2年でようやく掴めてきたように感じます。水産業界だから成長が遅くても良い、ということは一切なく、投資していただいた資金に対して高い成長速度でリターンを出し続ける。その覚悟がないなら、上場はすべきではないと痛感しています。
宮副:上場によって資金調達の選択肢も増え、M&Aも視野に入ってくると思います。買い手側として、どのような企業に魅力を感じますか?
山本:私たちの場合は、自社のプラットフォームと繋げることでバリューアップが見込める会社、特に事業承継の課題を抱える会社などを検討しています。M&Aで最も重視しているのは、その会社に言語化され、再現性のあるコアな価値があるかどうかです。例えば、特定の社長によって成り立っている属人的な強みだけでは、買収後に組織を拡大させていくことはできません。加工技術や独自のノウハウが、誰でも再現できる形で仕組み化されているかが重要です。以前、水産仲卸の会社を事業承継した際は、市場における「権利」と「場所」が明確なコアバリューでした。IPOによって社内体制が整い、資金的にも余裕ができたことで、こうした戦略的なM&Aを実行できるフェーズになったと感じています。
■ 宮副氏の挑戦
宮副:最後に私自身の話をしますと、創業当初からIPOを目指して走ってきました。しかし、AIの台頭など、世の中の変化があまりにも速く、1つのプロダクトを5、6年かけてスケールさせ、成長角度を維持・向上させることが、もはや至難の業だと感じています。単一事業ではなく、ポートフォリオを組んで複合的に成長エンジンを生み出し続けるような、これまでとは違う力学が必要だと痛感しています。幸い、弊社は外部から資本を入れていないため、時間的な自由度は高く、それが大きな強みです。この自由度を活かして、次の成長に向けたチャレンジを続けている最中です。
 写真左から)宮副氏、中村氏、山本氏
写真左から)宮副氏、中村氏、山本氏※「THE INDEPENDENTS」2025年9月号 P.7 より
※ イベント開催時点での情報です